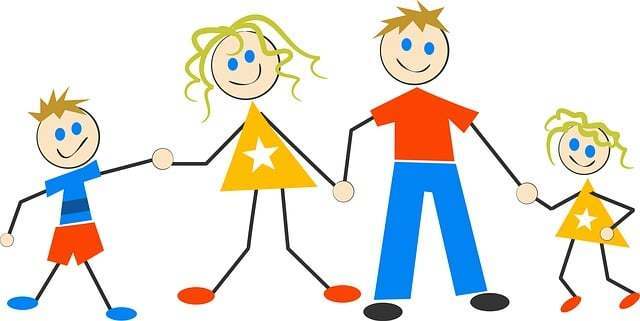日本とカリフォルニア州の弁護士資格者が国際離婚。国際相続をナビゲートします。

グローバル家族法コンシェルジュ
弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
〒105-6234 東京都港区愛宕2丁目5番1号
愛宕グリーンヒルズMORIタワー34階
営業時間 平日 9:00~18:00
03-5405-7850
子の親権・親子交流・養育費

こちらでは、子に関する問題について、ご説明いたします。
具体的には、「子の親権・親子交流・養育費」についてご説明いたします。
親権:単独親権

親権は、身上監護権、財産管理権、財産行為についての法定代理権等の個別の親権の内容を含んだものです。
離婚後は、2025年現在は、父母の一方の単独親権となります。
共同親権(2024年度民法改正)
2024年の民法改正により、2026年5月までに、離婚後、父母双方が親権を有することになる、共同親権を選択できる制度が施行される予定です。
離婚時に共同親権にするか、単独親権とするかについては、父母の協議で定めることになります(改正民法819条1項)。
協議で話しがまとまらない場合には、家庭裁判所が決定することになります。
裁判上の離婚の場合、裁判所が決定することになります(民法819条2項)。
くわしくは、下記をクリックしてご覧ください。
監護権

親権者とは別に監護者を定めることがあります。監護者が親権者とは別に定められた場合、監護者は、親権の内容のうち、子の監護および教育をする権利義務を有することになります。
ただし、離婚する際に、親権者とは別に監護者を決定することは少ないです。
調停・協議離婚の場合には認められることもありますが、審判・判決ではきわめて少ないといえます。親権者と監護者が分かれている場合、かえって、紛争を招いたりすることが多いからです。
親権者の決定

2025年現在、父母が協議上の離婚をするときはその協議でその一方を親権者と定めなければならないこととされています(民法819条1項)。
そこで、離婚届には親権者について定められていなければ、受理されません。
親権について協議がまとまらなければ、離婚の調停申立てをします。調停でも親権について合意ができずに、離婚の裁判となった場合には、裁判所が親権者について決定します(民法819条2項)。
Q では、親権者を決定するときには、どのような基準で判断されるのでしょうか。
A 「子の利益」を基準として、一切の事情を考慮して行われなければならないことになっています。
具体的には、次の①、②が重視されています。
① 監護の実績・継続性
現実に子を養育している者と子の心理的結びつきを重視することが子の福祉にかなうと考え、現実に子を養育監護している親が優先される傾向にあります。
ただし、子の年齢が高くなり、別居親との生活を希望すれば、子の意思が優先される傾向にあります。
② 子の意思の尊重
満15歳以上の子の場合、家庭裁判所は親権者の指定、子の監護に関する処分についての裁判をする場合には、子の陳述をきかなければならないとされ、子の意思が尊重されています。
それ以下の年齢の子であっても、およそ10歳の子の意思を尊重して親権者変更を認めた裁判例もあります。
このほか、少し前までは、特に子が乳幼児の場合には、母親が監護教育するのを不適当とする特段の事情のない限り、母を親権者とする、「母親優先の原則」が採用されていました。
しかし、今後は、一切の事情を総合考慮して総合的に判断されていく傾向に移行していくものとみられています。
親子交流

親権者でない親、監護者ではない親が子と交したり、手紙や電話でやりとりしたりすることを親子交流といいます(2024年の法改正により、面会交流から親子交流という言い方に変更になりました)。
民法改正により、現在では、民法766条1項により、「父と母又は子との交流」について規定されています。
親子交流については、子の利益を最も優先して考慮されることになります。親子交流について、調停で合意ができなかった場合には裁判所により審判で決定されます。
調停では、合意に至るように、調停委員会が働きかけることが多いようです。
親子交流が認められる際の判断基準
子に関するものとしては、
・子の心身の状況
・子の年齢
・子の意思
・親子交流が監護教育におよぼす影響
などが考慮されます。
親の事情としては、
・申立の目的(嫌がらせ目的ではないかなど)
・監護していない親の暴力
・監護していない親による監護親の監護方針に対する干渉
・監護親の再婚家庭の状況
などが考慮されます。
配偶者暴力(DV)で保護命令が発令された場合には、原則として親子交流が認められていません。
また、養育費を支払っても交流が認められない場合もあります。ケースによりますので過去の審判例などを参考に、ケースバイケースで考えていくことになります。
親子交流についての法律改正

親子交流(以前は面会交流という用語でした)については、法律改正により、次のとおり変更になりました。
親子交流の用語変更と制度導入(改正民法817条の13)
面会交流」という呼称が「親子交流」に変更されました。
親子交流の試行的実施(改正家事事件手続法152条の3/人事訴訟法34条の4)
家庭裁判所が、調停・審判の過程で、当事者に親子交流の試行的実施を促すことが可能となりました。
実際の交流を通じて親子関係の関係性を把握することができますので、その後の交流のあり方を決めるのに役立ちます。
父母以外の親族と子との交流の新設(改正法766条の2)
父母以外の親族(直系尊属(祖父母)や兄弟姉妹等が、裁判所が「子の利益のた特に必要と認めるとき」に子と交流することを認める制度が新設されました。
養育費

離婚後も、父母は、未成熟子に対して扶養義務を負います(民法877条1項)。
そこで、子を監護養育している親は収入に応じて、養育費を監護していない親に対して請求することができます。
養育費の算定
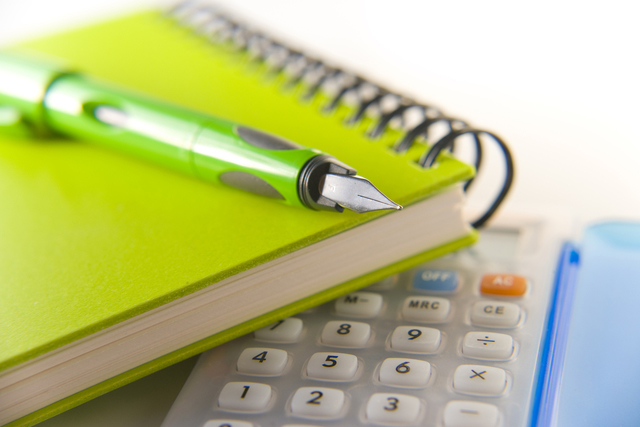
養育費については、調停・審判においても、標準算定表により、算定されています
算定表は、子が3人までの場合について、子の人数、年齢区分ごと(0~14歳、15~19歳)にまとめられた表です。
算定表では、養育費を支払う義務のある親(義務者)と支払いを受ける権利のある親(権利者)の年収をあてはめることにより、養育費の額を算定します。
ただし、算定表は標準的な養育費について記載されたものです。そこで、算定表で想定していない事案(たとえば、3人の子を父が2人引き取り、母が1人引き取った場合など)では、計算して相当な養育費の額を求めることになります。
具体的な計算は、ご相談の際に弁護士にお尋ねになることをお勧めいたします。
くわしくは、「算定表にない婚姻費用・養育費の計算」の項をご覧ください。
養育費の増減請求
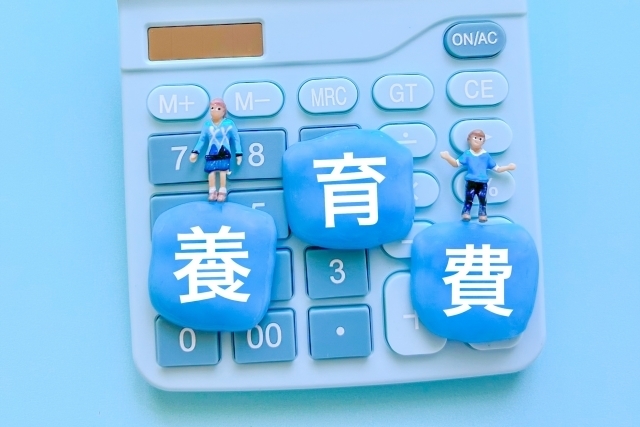
いったん取り決めた養育費については、その後に、父母の病気・失業などの事情変更があった場合、相手親に対して、養育費の増額・減額などを請求することができます。
養育費についての法律改正

2024年の法律改正により、養育費についても次のとおり改正されました。
遅くとも、2026年5月までに施行される予定です。
1. 養育費に関する扶養義務が明文化されました(改正民法817条の12第1項)
父母それぞれに、離婚後も子が自己と同程度の生活を維持できるように扶養する義務が明記されました。
2. 法定養育費制度の導入(改正民法766条の3)
離婚時に養育費の取り決めがない場合でも、「最低限度の生活維持に要する標準的費用」に基づく一定額を請求できる制度が創設されることになりました。
収入・事情に関係なく一律の法定額が算定されることになりました。
この制度の創設により、養育費について取り決めがない場合にも、一定の法定額が算定されることになり、収入について不明でも、一定程度の支払いが命じられることになりました。
3. 養育費債権への一般先取特権の付与(改正民法306条第3号・308条の2)
養育費債権に対して、他の債権者に優先して支払を受けられる先取特権(優先弁済権)が付与されることになりました。
これにより、養育費の回収可能性が高まることになりました。
4. 養育費執行手続のの簡易化(民事執行法167条の17)
財産開示・第三者情報取得・差押えまでを1回の申し立てで連続的に実施できるようになります。
これにより、手続が簡易になり、養育費の請求にあたり、請求する親の負担の軽減につながり、手続きの迅速化も進むことになります。
5. 収入・資産の情報開示命令制度の整備(人事訴訟法34条の3・家事事件手続法152条の2)
家庭裁判所が、養育費の請求において、当事者の収入や資産状況の開示を命じることができるようになります。
情報を開示しない場合、虚偽の情報を開示した場合には、10万円の過料に処せられます。
相手方の収入認定の際に役立つ制度です。
弁護士に依頼すべき場合とは

養育費について
養育費については、簡易算定表に基づいて請求する場合においても、相手方(夫)の収入算定にあたり、たとえば、相手方が自営業者の場合、どの金額を収入とみるかについて、法律的な判断が必要になります。
養育費について、離婚とともに請求され、調停で話し合いがまとまらない場合には、離婚の裁判で決められることになります。養育費のみが調停で申立てられた場合には、調停で話し合いでまとまらなければ、審判で裁判官が決めることになります。裁判、審判では、証拠を提出し、書面で婚姻費用の請求について主張しなければなりません。
そういった場合、法律的な知識が必要となり、弁護士に依頼する必要性があるといえますので、弁護士に依頼されることをおすすめいたします。
親権について
親権についても、どういった場合に親権が認められるかといった点について、法律的な知識と経験が必要となります。親権が認められる可能性が低いといえる場合には、親権取得を求めるのをやめ、お子さまとの面会交流を求めるということも考えられます。そういった見極めにも弁護士が代理人としていることで行うことが可能になります。
親子交流について
どういった場合に親子交流が認められるのか、親子交流についての実務を知った弁護士が代理人である場合の方が、親子交流を求めるにしても、親子交流を求められる側(相手方)の場合でも、スムーズな解決に至りやすく、望ましいといえます。