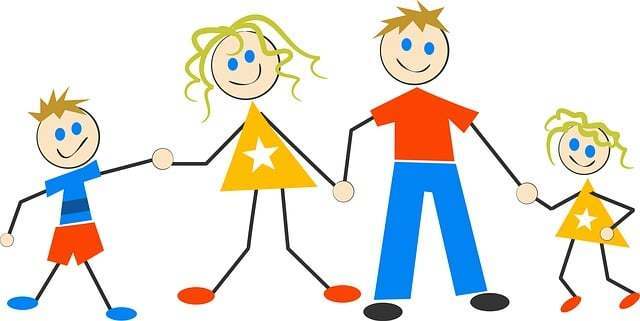日本とカリフォルニア州の弁護士資格者が国際離婚。国際相続をナビゲートします。

グローバル家族法コンシェルジュ
弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
〒105-6234 東京都港区愛宕2丁目5番1号
愛宕グリーンヒルズMORIタワー34階
営業時間 平日 9:00~18:00
03-5405-7850
算定表にない婚姻費用・養育費の計算

算定表が想定しているのは、子が3人までの場合で、権利者(一方の親)が子全員を養育している場合、給与収入が2000万円まで(自営の場合は1409万円)の場合です。
そこで、算定表が想定していない事案があります。
たとえば、
①複数の子を父母が別々に引き取っている場合
②4人の子どもを権利者(養育費を受け取る側)が引き取って養育している場合
③義務者(養育費を支払う側)が再婚して、新たな配偶者を扶養している場合などがあります。
いくつかのケースについて、計算方法をご紹介します。
ケース1 複数の子を父母が別々に引き取っている場合

長男が17歳、長女が7歳の場合、義務者である父親が長男の監護者となり、権利者である母親が長女の監護者となる場合
収入
父親の収入(給与所得)が650万円、母親の収入(給与所得)が150万円の場合について考えてみます。
計算方法には、いくつかありますが、算定表を利用した簡易な計算方法で計算します。
仮に、母親が、17歳の長男と7歳の長女を監護していたとすると、算定表(第1子15~19歳、第2子0~14歳の場合)から、2人の養育費の合計額はおよそ6万円程度と考えます。
生活費の指数が成人を100とすると、15歳~19歳の子は90、0~14歳の子は55と試算されます。
そこで、実際には、母親が7歳の長女だけを養育した場合には、2人の子の合計額6万円を長男:長女=90:55で分けることになります。
長女の養育費は、6万円÷(90+55)×55=約2万2758円
およそ、長女の養育費の目安は、約2万2758円となります。
ただし、これはあくまでも算定表を利用した簡易な方法ですので、一切の事情を考慮して、裁判所が計算した場合、多少、金額は異なることになります。
※ なお、ここでご紹介した以外にも、総収入から公租公課、職業日及び特別経費を控除して、「基礎収入」(養育費算定の基礎となる収入)を算出して計算する方法があります。
給与所得者の場合 基礎収入=総収入×0.34~0.42
自営の場合 基礎収入=総収入×0.47~0.52
ケース2 権利者が子4人を養育している場合

父(義務者)の年収(給与)700万円、母(権利者)の年収(給与)300万円、母親(権利者)が14歳以下の子ども4人を養育している場合を例として養育費を考えます。
計算方法には、いくつかありますが、簡易な方法で計算します。
子1人の算定表による算定結果に、子4人の配分を乗じて考えます。
生活費の指数が成人を100とすると、0~14歳の子は55と試算されます。
義務者世帯での子1人(14歳以下)の配分割合(子1人の生活費指数/子1人と義務者の生活費指数)と子4人(14歳以下)(子4人の生活費指数/子4人と義務者の生活費指数)の配分割合を比べます。
子1人(14歳以下)の配分割合:子4人(14歳以下)の配分割合は、
55÷(100+55):(55+55+55+55)÷(100+55+55+55+55)
これを計算すると、およそ、100:194となります。
算定表によると、義務者が支払うべき養育費(14歳以下子ども1人)は月額4~6万円となるので、これに、上記の配分割合を乗じると、
4~6万円×194÷100=約7,8~11,6万円となります。
この金額を目安に個別事案に即して判断することになります。
ただし、これはあくまでも算定表を利用した簡易な方法ですので、一切の事情を考慮して、裁判所が計算した場合、多少、金額は異なることになります。
ケース3 義務者が再婚して、配偶者を扶養している場合

父(義務者)の年収(給与)750万円、再婚して、無収入の再婚相手と5歳の子を扶養しているとします。
母(権利者)の年収(給与)300万円、母親(権利者)が6歳の子1人を養育している場合を例として養育費を考えます。
義務者が再婚している場合、再婚相手が無収入であれば、義務者は再婚相手を扶養する義務を負います。再婚相手との間に子が生まれれば、子についても扶養義務を負います。
算定表を利用する場合、義務者と同居する再婚相手の生活費指数は、子(0~14歳)と同じとされています。
ここでも、簡易な方法で算定表を利用して算定します。
すると、この場合には、養育費について、子が3人いる場合(0~14歳)と同じと考えられます。そして、そのうちの3分の1が義務者の支払う養育費の額ということになります。
子3人分の養育費は、およそ10万円ですので、その3分の1は、約3万3333円となります。
したがって、養育費の額は、約3万3333円となります。
ただし、これはあくまでも算定表を利用した簡易な方法ですので、一切の事情を考慮して、裁判所が計算した場合、多少、金額は異なることになります。