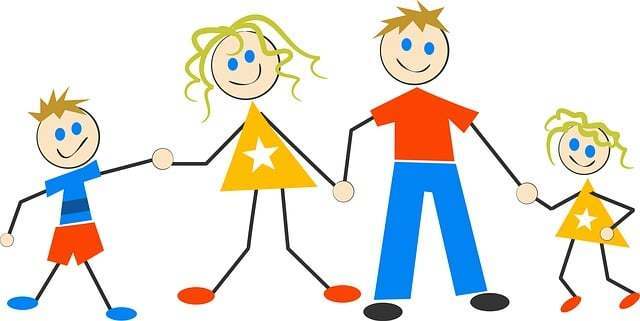日本とカリフォルニア州の弁護士資格者が国際離婚。国際相続をナビゲートします。

グローバル家族法コンシェルジュ
弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
〒105-6234 東京都港区愛宕2丁目5番1号
愛宕グリーンヒルズMORIタワー34階
営業時間 平日 9:00~18:00
03-5405-7850
代理母と特別養子縁組

日本法のもとでは、日本においては,生殖医療により子を懐胎し出産した場合に,出生した子の母は,その子を懐胎・出産した女性であるとされています(最高裁第二小法廷決定平成19年3月23日民集61巻2号619頁,判例タイムズ1239号1239号120頁参照)。
そこで、代理母を依頼した夫婦の妻は、子の実母とみなされません。
子と法律上の親子関係となり、実親との法律上の親子関係がなくなるためには、日本法のもとでは、特別養子縁組の成立が必要となります。
代理母による子の出産について、日本とは異なり、代理母を依頼した夫婦の妻と子に法律上の親子関係を認める国、地域もあります。
たとえば、カリフォルニア州では、子の誕生前に、裁判所の命令により、依頼した夫婦と子との法律上の親子関係を認めています(Pre-birth order).
アメリカは州により法律が異なりますので、代理母による子の出産の場合、依頼した夫婦と子との法律上の親子関係を認めるかどうかは、州により異なります。
法の適用(準拠法について)

代理母による子の出産の場合に、特別養子縁組成立のためには、養親、子が外国籍の場合、法律の適用(準拠法)が問題となります。
法の適用に関する通則法31条1項は、「養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。」と定めています。
養親が外国籍の場合、養親の本国法によって判断されます。
養親が日本国籍でしたら、日本法が適用になります。
養子となる子の本国法で、「その者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。」ことになっています。これは、保護要件といいます。
そこで、養子が日本国籍であれば、特別養子縁組の場合には、実父母の同意と家庭裁判所の許可が必要となります(民法817条の6、817条の2)。
たとえば、養親や子が二重国籍の場合、養親や子の本国法をがどこの地域の法かを検討しなければなりませんので、その点についても留意する必要があります。
Q) 養親の夫がフランスとドイツの二重国籍、妻がアメリカ国籍でカリフォルニア州の出身で、養子となる子が日本国籍の場合に、養親も子も日本に居住している場合、法の適用はどうなりますか

養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法によることになります(法の適用に関する通則法31条1項)
そこで、夫と妻の本国法が問題となります。
夫の本国法
夫については、ドイツとフランスの二重国籍ですので、本国法がドイツとフランスのどちらとなるかを考えることになります。
法の適用に関する通則法38条1項では、「当事者が二以上の国籍を有する場合には、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。ただし、その国籍のうちのいずれかが日本の国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする。」と定めています。
ここでは、夫は日本国籍ではありませんので、ただし書きはあてはまりません。
夫は日本に居住していますが、ドイツとフランスは含まれていませんので、常居所を有する国はないことになります。
そこで、当事者に最も密接な関係がある国はドイツかフランスかということになります。
様々な考慮要素により判断することになります。
ドイツに来日する前は居住しており、フランスには住んだことがないということでしたら、
ドイツ法が本国法となる可能性が高いといえます。
その場合、夫については、ドイツ法の養子縁組の要件をみたす必要があります。
妻の本国法
次に妻については、アメリカ国籍ですが、カリフォルニア州の出身とのことです。
法の適用に関する通則法38条3項は、「当事者が地域により法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある地域の法)を当事者の本国法とする。」と定めています。
アメリカでは、州ごとに養子縁組の法律が異なりますので、「地域により法をことにする国」ということになります。
そこで、妻については、カリフォルニア出身であり来日までカリフォルニアで継続して生活していた場合などは、カリフォルニア州法の養子縁組の要件をみたす必要があることになります。
子についての保護用件
子については、「養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。」と定められています(法の適用に関する通則法31条1項)。
そこで、子は日本国籍ですので、特別養子縁組の要件で考えますと、実父母の同意と家庭裁判所の許可が必要となります。
これらの要件を満たすことが、養子縁組のために必要となります。
代理母による子の出産の場合に、日本国籍の依頼した夫婦は、夫婦で共同して子と養子縁組をしなければなりませんか。

日本の実務のもとでは、代理母による出産の場合には、実母が法律上の親となります。
そこで、依頼者の夫婦については、たとえ、実父が依頼した夫婦の夫であった場合でも、子は依頼した夫の嫡出子とはならないことになります。
民法817条の3 1項は、「夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。」と定めています。
そこで、代理母による出産の場合、養親は夫婦共同縁組をすることが必要となります。