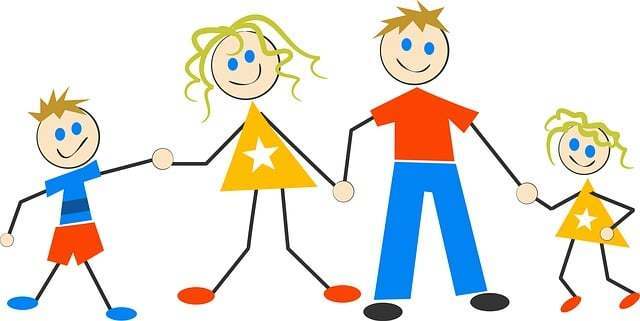日本とカリフォルニア州の弁護士資格者が国際離婚。国際相続をナビゲートします。

グローバル家族法コンシェルジュ
弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
〒105-6234 東京都港区愛宕2丁目5番1号
愛宕グリーンヒルズMORIタワー34階
営業時間 平日 9:00~18:00
03-5405-7850
日本における強制執行について

①子の返還の裁判が確定したにもかかわらず任意の子の返還がなされない場合、
あるいは、
②調停で子の返還を合意して調停が成立したにもかかわらず、または子の返還についての和解が裁判所で成立したにもかかわらず、約束の返還の期日までに子の返還がなされない場合、
子の返還について強制執行の申立てをすることが考えられます。
※履行勧告(121条)も考えられますが、子の返還についての強制力がない
ため、ここでは、省きます。
※子が執行時に16歳になってしまった場合には、執行が出来ないことになっ
ています(法135条)。
ハーグ条約実施法の改正前の問題点
ハーグ条約実施法の改正の前は、
① 間接強制を前置、
② 代替執行(解放実施)にあたっては、子と債務者(連れ去った親)の同時存在が必要とされていました。
具体的には、強制執行に際し、いきなり代替執行の申立てはできず、まずは間接強制の申立てを家庭裁判所に対してすることが必要でした。
間接強制とは、子が返還されないときに、「債務者(子を返還しない親)は、債権者(子の常居所地の親)に対し、~から上記引渡しの履行まで子1人、1日当たり、金5000円を支払え。」というように、子が返還されない場合に、子の引渡しまで一定の金銭の支払いを求める裁判を裁判所に求めるものです。
※実際の子の解放実施は、地裁の執行官が行います(法138条)。
子について代替執行をする場合、債務者(子を連れ去った親)が子と同時にその場に存在していなければなりませんでした。
しかし、間接強制を前置とすると、家庭裁判所の間接強制の決定に対して、債務者(子を連れ去った親)は高裁に不服申立てができるため、間接強制の決定の確定までに時間が要するということが問題とされていました。
また、代替執行に際し、子と債務者(子を連れ去った親)が同時に存在していないといけないことから、代替執行の実施に困難が生じるということがありました。
その他の問題もあり、ハーグ条約実施法の強制執行に関する規定が改正されることになりました。
ハーグ条約実施法の改正
ハーグ条約実施法が改正され、2020年4月1日より、施行されています。
改正法では、主に、
① 間接強制を必ずしも前置しなくてもよい場合が規定されました(改正されたハーグ条約実施法136条2号、3号)。
② 債務者と子の同時存在が不要となりました。
今後、ハーグ条約実施法の改正により、強制執行においてどのような変化がみられるか、については今後の事案の蓄積によることになると考えられます。
人身保護請求

代替執行による解放実施によっても、子の返還が実現しない場合、ハーグ条約実施法の範囲外の手続きですが、人身保護請求をすることが考えられます(地方裁判所、あるいは高等裁判所)。子の返還にあたり、最後の救済手段ともいえます。
代替執行による解放実施が不能となった案件で、人身保護請求がなされた案件で、最高裁第一小法廷は、平成30年3月15日の判決で(民集72巻1号17頁)、「実施法に基づき、拘束者に対して当該子を常居所地国に返還することを命ずる旨の終局決定が確定したにもかかわらず拘束者がこれに従わないまま当該子を監護することにより拘束している場合には、その監護を解くことが著しく不当であると認められるような特段の事情のない限り、拘束者による当該子に対する拘束は顕著な違法性がある」と判示しました。
最高裁は、子の返還決定に従わない子を連れ去った親による子の拘束について、原則として「顕著な違法性がある」と判示しました。
事案としては、高裁に差し戻しています。