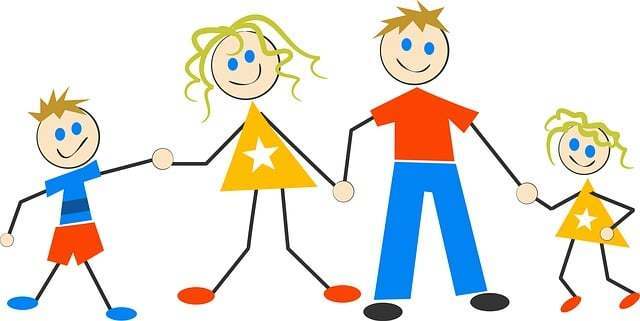日本とカリフォルニア州の弁護士資格者が国際離婚。国際相続をナビゲートします。

グローバル家族法コンシェルジュ
弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
〒105-6234 東京都港区愛宕2丁目5番1号
愛宕グリーンヒルズMORIタワー34階
営業時間 平日 9:00~18:00
03-5405-7850
カリフォルニア州で相続 VS.日本で相続

カリフォルニア州と日本では、相続手続きが異なります。
そこで、相続の際に、カリフォルニア州で財産がある場合、日本に財産がある場合の制度と手続きの違いについてご説明いたします。
カリフォルニア州の相続の制度と手続き

遺言(Will)と信託(Trust)があるかどうかで異なってきますので、分けてご説明いたします。
1. 遺言あり(Will)
(1) トラスト資産あり(信託:Trust)
- トラスト(多くはリビングトラスト)に不動産や金融資産を移している場合、信託の管理者(Successor Trustee)が直接管理・分配し、裁判所の関与なしで相続手続きを進めることができます。
- 裁判所の関与がなく、財産を換価して進めていくことができますので、より迅速に、通常は費用も抑えて手続きを進めることができます。
(2) トラスト資産なし(Willのみ)
- 遺言に基づき、不動産、預貯金、年金、株式などのプロベート(裁判所手続き)が必要になります。
- 年金や保険、預金の共同名義、Joint Tenancy with right of Survoivorship(生存者への移転の権利付不動産の合有)は、プロベートを回避する手段になり得ます。
- 気をつけなければならないのは、トラストに財産を移したつもりでも、トラストに移していない財産がある場合、みつかった場合、プロベートの手続きが必要になる場合があります。
2. トラストなし・遺言なし(Intestate)
- 遺言・プロベーとがない場合は法定相続となり、法律に従って配分されることになります。たとえば配偶者と子の場合、配偶者が1/2、残りを子で等分 することになります。
3. 少額遺産(Small Estate)手続き
プロベートなしで手続きをすることができます。
(1) 個人財産(Personal Property)の簡易取得手続き(Affidavit for Collection §13100–13101)
- 遺産の総額が一定額以下の場合( $208,850 以下 2025年4月1日以降の死亡者に適用)である必要があります。
- ただし、信託口座、共同名義、不動産(非居住用)、生命保険・退職金の受取人指定などは、価額計算から除外されます。
(2) 居住用不動産の簡易手続き(Succession to Real Property §13151–13154)
- 主たる自宅(カリフォルニア州内)の価額が 一定額以下の場合(2025年4月以降、$750,000 以下の場合、裁判所の小規模手続きで所有権移転が可能です。
- ただし、不動産の登記変更には裁判所命令が必要です。
4.財産によりプロベートの手続きを回避できる場合
不動産:所有権移転はプロベートまたはトラストによります。トラストであれば、裁判所の手続きが必要ありません。
預貯金:死亡時受取人指定(Payable-on-Death:POD)の口座や共同名義の口座(Joint Account)であれば、プロベート手続きが必要ありません。
年金・退職金:受取人(beneficiary)指定があればプロベートが必要ありません。
株式:トラスト名義であれば、プロベートが必要ありません。
日本の相続制度と手続き

遺言がある場合とない場合でその後の手続きが異なってきますので、遺言がある場合とない場合で分けてご説明いたします。
1. 遺言なし・相続人あり
(1) 協議による遺産分割
相続人が遺産分割について協議し、その内容に基づいて不動産登記換えや各金融機関手続きを行います。
合意が得られれば、裁判所の関与なしに手続きを行うことができます。
(2) 家庭裁判所の調停・審判
家庭裁判所で遺産分割の調停を申し立てます。相続人の間で合意ができなければ、審判の手続きに移行し、裁判所が決定します。
(3) 法定相続分
法律に基づき、法定相続分をそれぞれの相続人が取得します。
遺産分割で、法定相続分と異なる取り決めをすることもできます。
(4) 登記義務と期限
不動産は相続開始後3年以内に登記を完了する必要があります。
銀行預金や株式も解約や名義変更等の手続きが必要となります。
2. 遺言がある場合
遺言に従って、相続するのが原則です。
しかし、兄弟姉妹(場合により、甥、姪)以外の相続人には、遺留分が認められていますので、遺留分を侵害されている場合一定期間遺留分の請求が可能です。
3. 信託(トラスト)
日本では、信託はそれほど普及していません。
カリフォルニア州と日本の相続の制度と手続きのまとめ

・カリフォルニア州
トラストを活用すればプロベート(裁判所手続き)を避け、迅速に費用を比較的かけずに手続きを行うことができます。遺言だけでトラストの設定がありませんと、少額遺産手続きの場合や、共同名義の口座などの場合を除き、プロベートが必要となり、時間とコストがかかります。
資産内容に応じてトラストと遺言の組み合わせをすることが一般によく行われています。
日本
遺言がない場合、基本的に家庭裁判所の手続きによらずに、遺産分割の協議で相続手続きを行うことができます。
裁判所の手続きが必要となるのは協議がまとまらなかった場合です。
遺言がある場合、遺留分の請求に留意する必要があります。