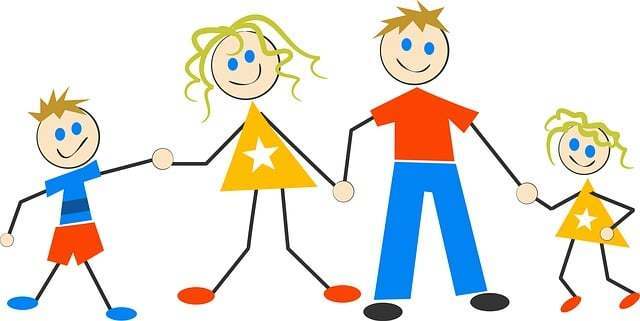日本とカリフォルニア州の弁護士資格者が国際離婚。国際相続をナビゲートします。

グローバル家族法コンシェルジュ
弁護士法人キャストグローバル東京事務所(担当弁護士 水内麻起子)
〒105-6234 東京都港区愛宕2丁目5番1号
愛宕グリーンヒルズMORIタワー34階
営業時間 平日 9:00~18:00
03-5405-7850
●相続の争いを未然に防ぐために

相続でもめて、兄弟仲が悪くなるといったことを聞くことがあります。これから、財産を遺そうと考えている方も、財産を受け取られる方にとっても、問題なく解決できることが望ましいといえます。
では、相続財産についての争いを未然に防ぐにはどうしたらよいのでしょうか。
相続財産を遺そうと考えている方(被相続人)と、相続財産を受け取られる方(相続人)に分けてご説明いたします。
これから相続財産を遺そうとお考えの方へ
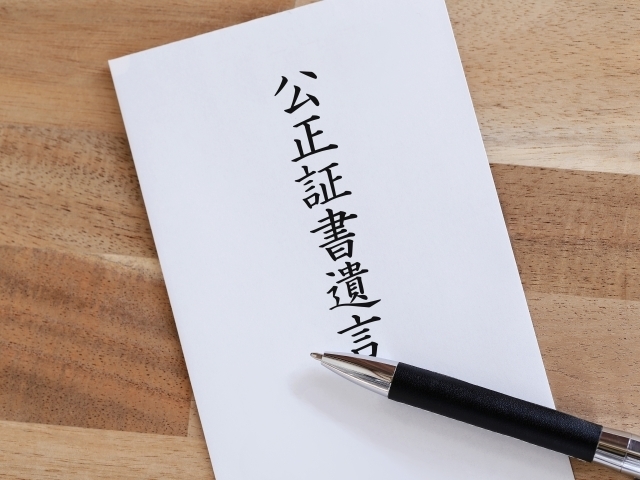
遺言がない場合、相続財産は、民法の規定に従った相続分により、法定相続されます。そこで、たとえば、相続人が、お子さん3人(長男、次男、長女)の場合、遺言がなければ、相続財産は3人に均等に分けられます。
もし、ご長男が、あなたの事業(たとえば、医院)を引き継いでいるなどの理由で、ご長男に全財産を遺したいとお考えの場合、遺言を作成されることをお勧めいたします。
遺言は、公証人役場で公正証書にされることをお勧めいたします。公正証書であれば、後に遺言が無効とすることが困難ですし、自筆証書の場合とは異なり、家庭裁判所で検認手続きという手続きを経る必要がないからです(法改正により、法務局で自筆証書遺言が保管されている場合には、検認手続きが不要となりました)。
ただし、遺言を作成する場合、相続人の遺留分を侵害しないようにすることにも配慮が必要です。遺留分を侵害した内容にする場合、たとえば、全財産を取得した相続人に対して、遺留分侵害額請求がされて、相続財産をめぐる争いが起きてしまうことも考えられるからです。
具体的な遺言の内容については、ぜひ、ご作成にあたり、弁護士等の専門家にご相談をされることをお勧めいたします。
相続財産を受け取られる方へ

遺言がある場合、遺言がまず、有効かどうかを考えてみてください。自筆証書遺言の場合、筆跡がご本人のものかどうか確認が必要です。
遺言が有効な場合、遺留分が侵害されているかどうか、ご確認ください。
ただし、遺留分については、請求について期間制限(改正民法1048条)があるので、留意が必要です。期間をすぎると、請求できなくなります。
遺言がない場合は、相続人の相続分にしたがって、法定相続することになります。この場合に、寄与分、特別受益なども考慮されることになります(法律改正により、相続人以外の親族の貢献を考慮する、特別な寄与料の支払いの制度が設けられました。
ご自分がどのような権利を法的に主張することができるかを知ることが、相続財産についての争いを防ぐための一番の近道ではないかと考えます。
法的な権利を知ったうえで、遺産分割協議にのぞむことが必要といえます。遺産分割協議で決着がつかない場合、一般には、遺産分割の調停で話しあうことになります。
また、仮に、被相続人が亡くなる前に、被相続人の預貯金通帳を預かっていたような場合に、親族だからよいだろうと考えて、預金を使い込んでしまいますと、あとで、ほかの相続人から、不等利得返還請求をされるおそれもありますので、留意が必要です。
相続についてどのような法的な権利があるかについては、ぜひ、弁護士等の専門家にお尋ねください。